100億企業化
100億企業化へのM&A―②―
2025.09.17
▼『100億企業を実現した5人の経営者の成功事例』 無料ダウンロードはこちら
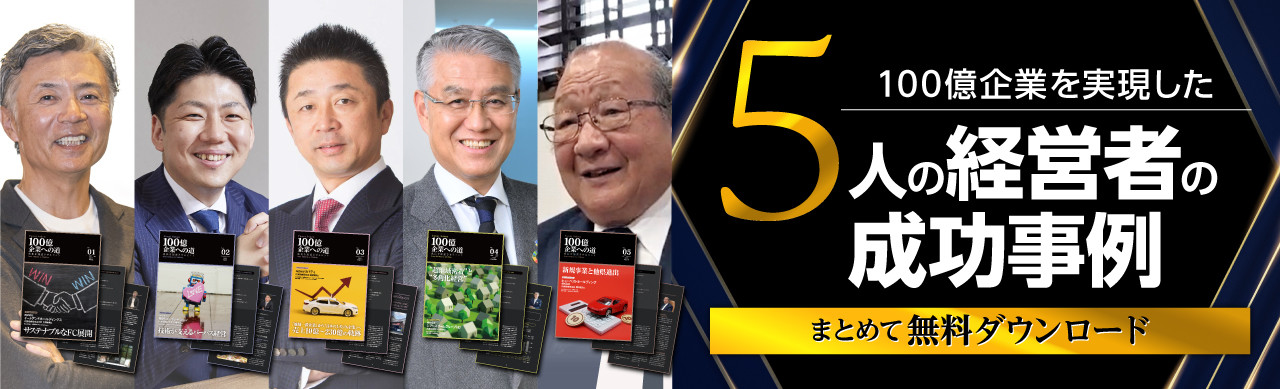
いつもお読みいただき、誠にありがとうございます。
株式会社船井総合研究所 取締役専務執行役員兼、
株式会社船井総研あがたFAS 代表取締役社長の出口 恭平です。
船井総研グループでは、2025年の1月に、事業承継・M&Aを専門とするグループ会社、船井総研あがたFASを立ち上げ、譲渡側・譲受側両方のM&Aのサポートをおこなっています。
100億を目指す企業の皆様にとって、選択肢の1つとして情報収集いただきたいテーマですので、本コラムにて詳しく解説させていただきます。
※前回の内容はこちら 100億企業化へのM&A―①―
買い手としてM&Aを成約に導くには
昨今、M&A仲介会社が視力のない買い手を紹介して、トラブルを起こしたことがニュースになる等、M&Aを巡るトラブルが報道されることが増えました。M&Aの件数は増えているが、うまくいっていないケースも多い等、報道されることもあります。
世の中の企業の経営が全てはうまくいっている訳ではなく、うまくいかないケースも多くありますので、同じように、M&Aをしてもうまくいかないこともあるだろうとは思いますが、M&A仲介会社が、M&Aした後の両社の経営に責任を持たずにマッチングする、というのは、とんでもないことだと思います。
当社・当グループもコンサルティングでお付き合いさせて頂いている企業様からM&Aのご相談(譲渡側、譲受側のの両方で)を頂くことが増え、7-8年前から、M&Aのアドバイザリーや仲介も行っています。100億を目指す企業様が、M&Aで事業を拡大されるケースも随分と増えてきました。
M&Aが成約するかどうかは、売り手(譲渡オーナー様)、買い手(譲受企業様)双方の相性もありますし、条件が合うかどうか等々、様々な要素があります。
しかし、買い手として、M&A巧者の企業様、経営者様は、当初の条件が多少条件が合わなくても、売り手企業のオーナー様が一癖も二癖のある場合でも、この企業と一緒になりたい、となれば、いくつもの課題を乗り越えて、M&Aを成約に持っていかれます。
これまで、様々なM&Aに伴走させて頂いて、それは必ずしも、良い条件を出しているかどうか、ということではない、ということを痛感しています。中堅・中小企業のM&Aにおいて、M&A巧者の経営者の一番の共通点は、お相手の経営者様との信頼関係を作るのが上手、ということです。
オーナー企業様のM&Aは非常にセンシティブで、オーナー経営者様は自分が手塩にかけて育ててきた会社を手放すことに、心理的な抵抗が極めて強いのです。そのため、ちょっとしたことで「この企業に譲渡して大丈夫かな」、「やっぱり譲渡しない方が良いかな。」というマインドになってしまうことがあります。
そのようなオーナー経営者の心理をご理解され、信頼関係の構築にたけた経営者は、多少条件面のズレがあっても、それを成約までもっていかれます。
逆に「如何に良い条件であっても、譲渡企業のオーナーと信頼関係が築けない場合は、悪い予感がするので、M&Aを断念することもある。」とおっしゃる経営者様もいらっしゃいます。
当社・当グループでも、M&Aの仲介に入らせて頂く場合には、条件面の調整以前に、どのように譲渡側の経営者様と、譲受側の経営者様の信頼関係を構築して頂けるか、ということが一番のテーマであると考えています。
M&A後のPMIで業績を上げる
PMI(ポスト・マージャー・インテグレーション)という言葉も、随分と浸透してきました。PMIとはM&A後の統合効果を最大化させるための統合プロセスを指します。
PMIにおいては「100日プラン」というのも一般的な用語になりつつありますが、これは制約から100日間の施策やスケジュールのことを指しています。
これまでにも述べましたが、昨今のM&Aの失敗事例について、世の中の企業の経営に失敗があるように、M&Aにも失敗はあるだろうから、それを仲介会社のせいにするのはおかしい、とは思いますが、一方で、日本ではこの10年間で、大きな収益が得られるからと、中堅・中小企業のM&A仲介会社がこれだけ増えてしまって、M&A後のPMIをやる会社は全然増えていないのは如何なものか、とは思います。
大企業であれ、中堅・中小企業であれ、M&Aを成約に導くためには、PMIが重要であることは誰も異論がないところかと思います。そして、これが口で言うのは簡単であるけれども、実際にやるのは非常に難しい、というのも、同じく誰も異論がないことかと思います。
100億を目指す企業がM&A巧者となり、M&Aによって成長し、100億化を実現するためには、M&Aの成約と同じぐらい、PMIを重視する必要があります。
現実的に、成約から100日間で一定の成果を出すためには、成約以前から、どのようにその効果を出していくか、業績を上げていくか、相乗効果を出していくか、プランニングが出来ていることが重要です。プランニングまでいかなくとも、「こうすれば、うまくいく」、「こうすれば、自社にグループインした効果が出せる」というイメージが出来ていることが前提になります。
その上で、成約後できるだけ早いタイミングで、譲渡側オーナーは勿論、幹部陣、キーマンと信頼関係を構築し、グループとしてどのような方向性を目指すのか、というビジョンに共感してもらうこと、100日間で目に見える成果を示して、明るい未来を見せていけるかどうか、ということが重要になります。
一方で、現場は、事業のビジョンや会社の将来像がどうのこうのと言っても、それ以前に、オーナーが変わったことで、雑事が増えたり、今までと仕事の進め方が違ったり、ということをストレスに感じて、不満を抱えてしまい、業務が逆に停滞したり、思わぬ規模の離職が出たりもします。
このような現場レベルの不安や不便、不満を解消しつつ、新たな方向性を示す、そして結果を出す、といことが重要になります。
M&Aを実行する体制
難しいテーマの文章を設定してしまいました。
船井総研グループの売上は約300億ですが、当グループのM&Aを推進する担当は、専任では2名です。
もちろん、実際にM&Aを実行する際には、CEOもCFOも関わりますし、PJチームを組成して動くことになります。
それにしても、常時、自社のM&Aを専任で動いているのは2名なわけです。
通常、売上100億を目指す企業様となると、一部の例外を除いて、M&Aを専任で担当するメンバーはおられないことが殆どです。
社長とCFO又は社長室や社長付きの特命メンバーが中心となって実施する、ということが殆どかと思われます。
ズバリ100億企業化に向けて、M&Aを実行する体制を整える場合、その担当には社長の右腕を充てるべきです。
当社・当グループがM&Aのアドバイザリーや仲介をさせて頂いている経験上、一番の理想は、
「社長がいて、今まではナンバー2に既存事業の現場を任せていた。それが、ナンバー3に既存事業の現場を任せられるようになった。そこで、ナンバー2を新規事業やM&A等、新しい攻めの分野の責任者に据えることができるようになり、M&Aの初期段階からナンバー2にも入ってもらい、PMI段階でもナンバー2が入る。或いは、強引にでも、ナンバー2を既存の現場から外して、新規に当ててしまい、ナンバー3に既存を引き継がせる。」
これが1つの形です。
場合によっては、既存事業の現場をナンバー2に任せて、社長が新規事業や、M&Aの方に注力する、というパターンもあります。
いずれにせよ、100億を目指す企業でM&Aを成功させるためには、エース人材をM&Aの実行やその後のPMIに充てることは必須です。エース級の人材は既存事業を支えているから、そこから抜けられない。M&Aに充てられるのは、既存事業から浮いているメンバー、というのでは、残念ながら失敗する確率が高いと言わざるを得ません。
しかし、これから100億を目指す企業様においては、トップやナンバー2、ナンバー3が、既存事業に執着するのではなく、これまで自分が担当していた領域を次のメンバーに譲って、自分は新しい事業やM&Aに挑戦する、そうやって、事業を拡大し、メンバーが育つ環境を創っていける、そのような好循環を生み出していくことが重要になると思います。
貴社の事業や実情に合わせて、100億企業化に向け、どのようなM&A戦略の選択肢があるのか、現実的にどのような戦略的M&Aが可能か、一度自社の選択肢としてご検討いただいては如何でしょうか。
当社・当グループでは、様々な業界のM&Aの状況を把握・情報提供に努めています。
またM&Aのアドバイザリーや仲介をさせていただいた際には100%、PMIのご提案もしております。また、当社・当グループがM&Aのアドバイザリーや仲介でない場合の、PMIについてのご相談も承っています
ご関心のある方は遠慮なくお問い合わせいただければ幸いです。

100億企業化
コンサルティングに
ついてはこちら
お問い合わせ
CONTACT



