人事組織
会社を動かし、幹部を育てる経営方針発表会のあるべき姿と成功事例
2025.03.03
▼『100億企業を実現した5人の経営者の成功事例』 無料ダウンロードはこちら
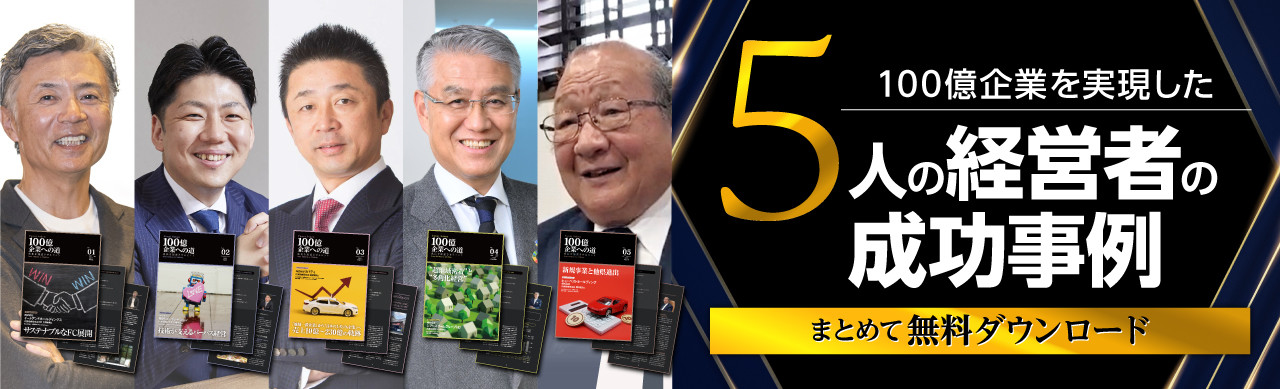
~方針発表会のあるべき姿・役割編~
いつもお世話になっております。
株式会社船井総合研究所 アカウントパートナー推進部の鳥居 勇志でございます。
企業の成長を加速させるためには、社員一人ひとりが同じ方向を向き、同じ目的・目標に向かって進むことが不可欠です。
特に社員が100名前後になってくると、社長が社員一人ひとりと向き合える時間はかなり限られてきます。
そのため、社長の考え方・価値観が伝わり切らず、会社の目指したい姿と社員の頑張るベクトルがズレはじめ、成長が鈍化しやすい傾向にあります。(社員から見た時に、社長が遠い存在になる)
会社の目指したいところと、社員の意識を揃える施策は様々ありますが、今回は「方針発表会」を活用してさらなる成長を目指すためのポイントと事例をご紹介します。
(経営)方針発表会とは?
すでに毎年実施されている企業も多いかと思いますが、方針発表会とは、経営理念やビジョン、年間目標、具体的な行動指針などを全社員に共有し、浸透させるための場です。
単なる計画発表の場ではなく、社員一人ひとりが「会社がどこへ向かおうとしているのか」「自分は何をすべきなのか」を明確に理解し、主体性と責任感を持って業務に取り組むための場であるべきです。
方針発表会のあるべき姿・役割
➀社員がワクワクすること
方針発表会の最も重要な役割です。会社の未来に対する期待感や、自身の成長への意欲を高めるような、ワクワクする内容であるべきです。
➁社員の会社理解・会社の将来像理解度を高めること
会社のビジョンや戦略を共有することで、社員は会社全体の進むべき方向を知ることができるわけですが、会社の将来像をイメージできることで、はじめて社員は自身の役割や立ち位置を認識することができます。
そして、会社の目指す姿と自身の現状を比較することで、やるべきことが鮮明になり会社の目指す姿に沿った社員の意識や行動に変えていくきっかけになります。
➂理念浸透・社員の帰属意識向上させること
経営理念やビジョンを共有することで、社員の帰属意識を高め、一体感を醸成することができます。特に、会社の考えに納得感を抱いたり、発表内容が腑に落ちた時、自分にとって重要なことだと認識した時に帰属意識が高まります。
④(すでにロードマップ(中長期方針等)がある企業の場合)幹部候補・若手のモチベーション高めること
会社の将来像を明確に示し、幹部候補や若手社員に自身の将来を考えさせることで、幹部としての意識や考え方を刺激できます。
また、社長だけでなく幹部・幹部候補からの情報発信の場を設けることで、会社全体のこと考える経験を得ることができます。
方針発表会の事例~売上約30億円の会社~
●会社の概況
・主力事業が成熟化しており、未来の描き方・伝え方に悩んでいた。
・毎年同じような内容になっており、マンネリ化を感じていた。
・社長は新規事業や生産性向上に意欲はあるが、安定している業界であるがゆえに社員には「変化」や「新しい取り組み」に肯定的な社員は少ないように感じていた。
●実際の方針発表会の大まかな内容
・これまでの感謝:社員への感謝の気持ちを表明
・これまでの歴史と昨年の振り返り:創業からの歩みと昨年度の成果を共有
・外部環境の変化と自社の立ち位置の認識を共有
・来年は、社員の幸せを目指す:社員の幸福度向上を目標に設定
・そのためには生産性の向上が必要不可欠:生産性向上のための施策を紹介
・幸せ実現のためにすでに始めている施策の紹介:具体的な取り組み事例を共有
・社員の幸せ・生産性向上に向けたさらなる今後の展望:将来への期待感を高める
●特に想いを込めた箇所・ポイント
【外部環境の変化を捉えた、成長戦略を描いた点】
元々は、成熟産業ということもあり、よく言えば安定していることを他伝えるために、「同業は減ってはいるがまだ◯◯◯社も残っているため、まだ当分は安心できる」という内容から「顧客数の減少以上に同業者の数が減少しおり、シェア率を高めることでより成長していくことができる」と変更し、「挑戦」や「成長」のイメージを盛り込んだ。
【最も伝えたいことを「生産性向上」から「社員の幸せ」に変えた点】
元々は、今季の目標として「生産性向上」を考えていたが、社員の幸せ実現のために、生産性向上が必要というストーリーにした。
結果、会社目線のやりたいことより、社員目線で嬉しいことが優先されたため、社員の腹落ち感・納得感を重視した内容にできた。
●方針発表会後の変化・参加者の感想
「参加した社員の感想としては、多くの社員からモチベーションが上がったとの感想が聞けた。」
「方針発表会後の部門別ワークの時間で、これまで以上の活発な議論ができ、社員の積極性が高まった。」
「参加した外部の方(取引先)からも、『いままでで一番良い方針発表会だった。外部環境の変化を踏まえた自社の立ち位置と未来像はうちでにも取り入れたい視点だった。』という感想が聞けた。」
方針発表会の構成・内容
効果的な方針発表会を行うためには、以下の要素を盛り込むことを意識しましょう。
●(前提として)過去の話3割、未来の話7割がベストな比率
方針発表会では、ついつい過去の話・昨年の振り返りをしてしまう企業も多いです。しかし、過去の話をしても社員のモチベーションを高めることには繋がりにくいです。
過去の話は「感謝」を中心に、業績推移や経営指標の変化、会社の歴史、昨年の取り組みも含めて前半の3割にとどめ、いかに未来の話に時間を割くかが重要です。
●会社目線と社員目線の優先順位とバランスを意識する
会社の視点だけでなく、社員の視点も取り入れることで、共感を得やすくなります。
例えば、「生産性向上」は会社目線になります。社員にとって生産性が上がることは会社都合に映る可能性が高いです。
一方で、幸せを増やす・手取りを増やすなどは社員目線であり、社員にとって考えやすいテーマになります。
発表の流れとしては「社員の幸せを作る」→「そのためには生産性を上げる必要がある」というように、会社のためではなく、社員のため(社員目線)となるようなストーリーにすることが重要です。
発表したいことの主語が、「会社が」なのか「社員が」なのか混同しないように注意しましょう。
●外部環境の現状と予測を盛り込む
社会情勢や業界動向、会社を取り巻く環境を共有したうえで、会社の立ち位置を伝え、そのうえで取るべき戦略・取り組む施策を伝えることでストーリー性が生まれ社員の納得感・腹落ち感を高めることができます。
●発表内容を誰に伝えたいのかを明確にする
多くの会社で、いろんな世代・職種がいる中で、全員に関わる話を中心にしたいという経営者さんが多いですが、全員に関わる内容は話の内容が浅くなりがちな傾向があります。幹部候補や若手社員など、特に伝えたい層を意識したメッセージを入れることで、より効果的に訴求することができます。
あたりさわりのない内容は、無関心を生みます。方針発表会の内容を特に伝えたい人の名前が挙がるくらい、対象の絞り込みをすることで、「刺さる方針発表会」を作ることができます。
●幹部育成の場としての方針発表会という視点を持つ
社長だけでなく、幹部や社員からの発信も取り入れることで、会社全体に対する発表の経験、会社の中長期イメージ・戦略を考える経験を積むことができます。
また、社員100名の会社の場合、現場を引っ張るのは社長ではなく幹部になります。社長からの発信よりも幹部からの発信の方が現場社員に刺さる方針発表会を作ることができます。
具体的な構成例(案)を紹介します
1.導入
会社の現状や課題認識を共有し、方針発表会の目的を明確にする
マインドセット:方針発表会の受け方・聞き方を共有
2.過去の話(全体の3割)
感謝:社員への感謝の気持ちを伝える
会社の歴史・大切にしたい価値観:創業の精神や企業文化を共有
業績推移・経営指標:過去の業績を振り返り、現状を認識
昨年度の振り返り(全社・部門別):成功と失敗から学び、改善点を共有
3.未来の話(全体の7割)
地域・社会・経済の未来イメージ:社会の変化を捉え、将来展望を共有
自社の未来イメージ:目指す未来、ビジョンを明確に提示
中長期戦略と中期経営計画と単年度戦略(方針):具体的な目標と行動指針を示す
幹部・幹部候補の発言・意気込み:リーダーシップを発揮し、社員を鼓舞
4.まとめ
行動への呼びかけ:社員一人ひとりの行動変容を促す
質疑応答:疑問点を解消し、理解を深める
最後までお読みいただきありがとうございました。
~攻めた未来を描くために船井総研ができること~
船井総研では中長期の視点で会社経営を考えることを推奨しております。
というのも、売上20億~30億を超えたあたりから企業の成長は鈍化するとされており(成長の壁)、この成長の壁は50億前後、100億前後でも発生するとされています(業種によって差あり)。
そういった中で、当社では成長の壁突破に必要な視点・戦略を研究しており、その研究成果(成長の壁突破の答え)がかなり見えてきております。
それらをもとに、皆様の未来を一緒に描ければと思いますので、お気軽に当社コンサルタントへお問い合わせください。
>無料経営相談の流れを見てみる

100億企業化
コンサルティングに
ついてはこちら
お問い合わせ
CONTACT




