財務戦略
100億企業化を実現する財務戦略【資金調達の最大化】
2025.07.28
▼『100億企業を実現した5人の経営者の成功事例』 無料ダウンロードはこちら
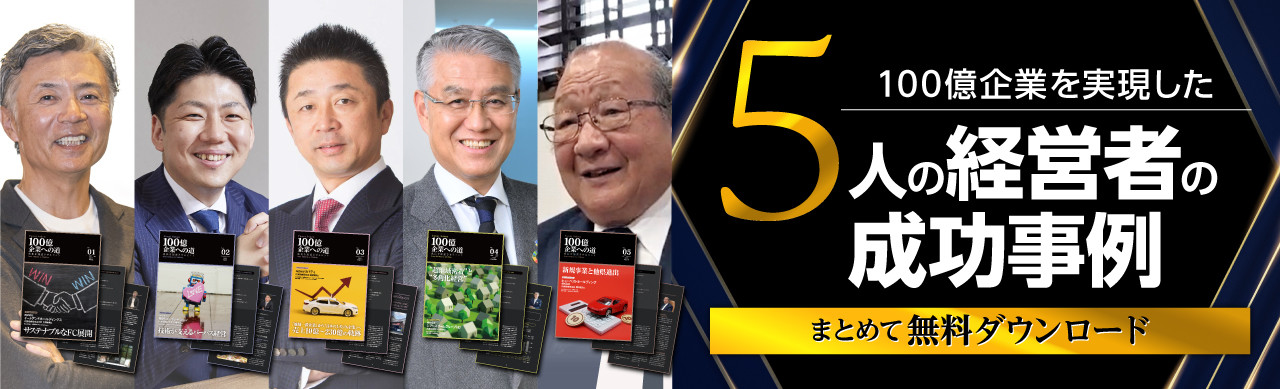
いつもお読みいただき、誠にありがとうございます。
船井総合研究所 アカウントパートナー推進部の谷 翔太です。
売上高100億円という目標を達成するためには、これまでの延長線上にある財務戦略では不十分です。
事業への積極的な投資が不可欠であり、その投資を支えるために「資金調達によってレバレッジをかけ、成長を加速させる」という発想が求められます。
これは「投資財務戦略」と呼ばれ、企業の持続的な成長を実現するための投資活動と、それを支える強固な財務体制の構築を指します。
成長を加速させる資金調達の重要性
企業にとって資金は事業活動の生命線であり、100億円企業化への道のりにおいては、この資金をいかに戦略的に活用するかが成功の鍵を握ります。
中小企業庁の調査によると、売上高100億円を達成した企業の成長初期における借入金は総資産の37.7%にも達すると報告されています。
これは、企業が成長を加速させる上で、外部からの積極的な資金調達が不可欠であることを明確に示しています。
たとえ現時点で財務状況が極めて健全で、金融機関から融資を勧められるような状況であっても、将来的な大規模投資に備え、「必要な資金は前もって確保しておく」という姿勢で金融機関との関係を構築し、資金繰りの安心感を高めることが重要です。
財務部門はもはや単なる「金庫番」ではなく、事業成長を積極的に後押しする「攻めの財務」へとその役割を変革していく必要があります。
金融の「空白地帯」を突破する多行取引戦略
100億円企業化を目指す上で多くの企業が直面する財務課題の一つに、「取引金融機関数が不足している」という点があります。
日本の金融業界は、企業の規模に応じて対応する金融機関が異なるという特性を持っています。
例えば、信用組合や信用金庫は主に小規模企業を対象とし、地方銀行は売上高20億円から50億円程度の企業を主要顧客としています。
しかし、売上高70億円以上の企業を主な対象とする都市銀行との間には、売上高50億~70億円規模の企業層に対する「金融の空白地帯」が存在すると言われています。
この空白地帯に位置する企業は、適切な資金調達が難しくなり、事業成長が足踏みしてしまうリスクを抱えることになります。
この課題を克服するための現実的な戦略が「多行取引」です。
単一の金融機関から事業拡大に必要な何十億円もの資金を調達することは困難であるため、複数の金融機関と戦略的に取引関係を構築していくことが重要となります。
多行取引は単に取引金融機関の数を増やすだけでなく、「バンク・フォーメーション」という概念を意識し、自社の規模拡大に合わせて、より多くの融資余力を持つ金融機関との取引を強化していくことが求められます。
例えば、売上高が20億円規模を超えた段階で地方銀行からの借入額を増やし、その後、100億円企業化を視野に入れながら段階的に都市銀行との取引を本格化させるなど、企業の成長ステージに応じた計画的な関係構築が必要です。
実際に、創業から短期間で売上高100億円に到達した企業の中には、40行を超える金融機関と取引を構築し、大規模な資金調達を可能にした事例もあります。
これは極端な例ではありますが、都市圏以外の地域においても、20行程度の金融機関との取引が資金調達力を高める目安となることが示唆されています。
また、M&Aを積極的に活用し、短期間で急成長を遂げた別の企業では、約30社の金融機関と取引関係を構築し、「借りられるだけ借りる」という積極的な姿勢で資金調達を進めた事例も存在します。
これらの事例は、成長企業にとって多行取引がいかに重要であるかを示しています。
金融機関を味方につける「決算説明資料」の実践
金融機関から継続的かつ有効な支援を受けるためには、「積極的な情報開示」と「密な対話」が不可欠です。
近年、金融機関の融資判断は、かつてのように決算書の数字(定量評価)だけではなく、企業のビジネスモデルや将来性といった定性的な要素を重視する傾向にあります。
しかし、金融機関側の担当者交代(一般的に約2年サイクル)や人員減少により、企業の実態を正確に把握し続けることが難しくなっているという現状もあります。
そこで、企業側から戦略的に情報を開示する「決算説明資料」の作成・実施が非常に重要になります。
決算説明資料では、損益計算書(P/L)や貸借対照表(B/S)の実績値だけでなく、業績変動の要因、具体的な施策、今後の事業展開などを具体的に共有します。
特に、金融機関が重視する自己資本比率や債務償還年数といった財務指標を明確に示し、さらに事業計画の具体性を裏付ける月次管理の状況なども開示することが、信頼構築のポイントです。
決算説明資料の作成と、それに基づいた金融機関との個別面談は、金融機関との対話を深め、自社への理解を促進し、良好な関係性を強化するために極めて有効です。
決算後の適切なタイミング(例えば3月決算であれば6月頃)に、主要な金融機関ごとに個別面談を実施し、自社の調達方針や今後の投資計画を具体的に伝えることで、将来の資金調達を円滑に進めるための強固な基盤を確立できます。
これにより、金融機関は「この会社に融資することは自社にとってメリットがある」と認識し、社内での融資稟議を積極的に進めてくれる「自社の代弁者」となってくれる可能性が高まります。
財務体制の強化とCFOの役割
資金調達戦略を円滑に推進し、持続的な成長を実現するためには、財務を担う組織体制の強化が不可欠です。
特に、CFO(最高財務責任者)を中心とした体制を確立し、財務に関する権限を適切に委譲することが極めて重要となります。
CFOは単なる経理実務の責任者ではなく、企業価値の向上や経営課題の解決のために、経営的・事業的な視点から戦略的に動く「戦略家」としての役割を担います。
CFOが資金調達、投資判断、財務リスク管理といった高度な財務戦略を主導することで、経営者は本来の業務である事業戦略の策定や意思決定に時間を割くことが可能となり、金融機関との面談への対応も円滑に進められるようになります。
現状、多くの企業で銀行対応や財務管理が社長に属人化しているケースも少なくありません。
このような状況を改善するためには、財務専任の担当者、特に金融機関での実務経験を持つ人材の採用が推奨されます。
彼らは財務に関する深い知識と金融機関との交渉経験が豊富であるため、即戦力として期待できます。
また、組織的な財務管理体制の構築(財務PDCAサイクルの実践や、貸借対照表・キャッシュフロー計算書を中心とした財務管理の徹底など)を推進し、企業全体の財務力を底上げする上で重要な役割を果たすでしょう。
100億円企業化という目標達成には、資金調達戦略の巧みな実行が不可欠です。
適切な資金調達、強固な金融機関との関係構築、そしてそれを支える盤石な財務体制の確立こそが、企業の成長を加速させる原動力となります。
この「攻めの財務戦略」をどのように構築し、実行していくか、を具体化してくことが重要です。
お気軽にご相談ください。

100億企業化
コンサルティングに
ついてはこちら
お問い合わせ
CONTACT




