お好み焼き屋から海外事業まで 広島マツダが異業種参入で実現する成長戦略/株式会社広島マツダ
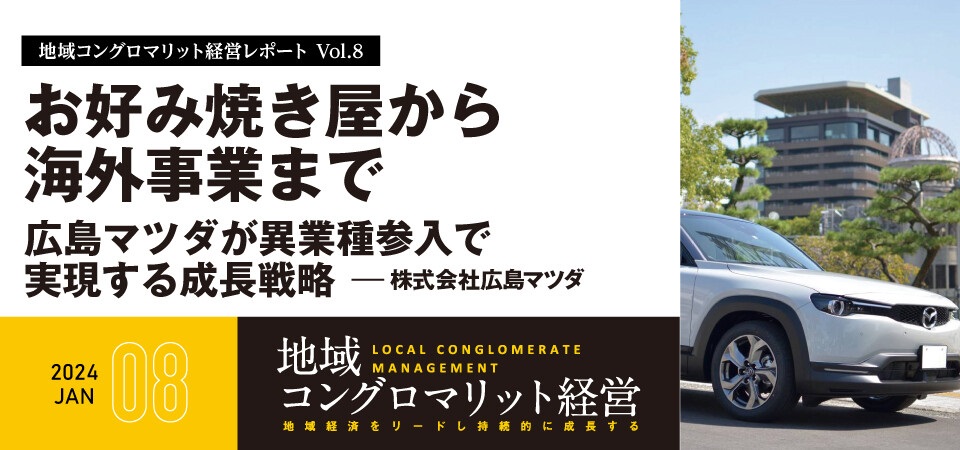
目指したのは「マツダ創業の地の自動車販売店」からの脱却
広島マツダは、マツダの自動車を広島で販売している会社です。
現在、その事業はクルマの販売や整備にとどまらず、観光・飲食事業やデジタル、人材紹介・派遣や不動産など多岐にわたり、売上高は222.7億円、経常利益4.1億円に上ります。広島において確固たる地位を築いており、まさに地域コングロマリット経営を実践している企業です。
自動車関連事業以外への進出を主導した広島マツダの代表取締役会長兼CEO の松田哲也氏に、経営に関するお考えをお聞きしました。
船井総合研究所の鈴木圭介との対談形式でお届けいたします。
インタビュー&レポート

株式会社広島マツダ
代表取締役会長兼 CEO
Tetsuya Matsuda
松田 哲也氏
鈴木:
広島マツダは1933年にマツダの2代目社長である松田重次郎氏の次男、松田宗弥氏が広島での販売・整備を行う企業としてマツダモータースを創業したことから始まります。
1956年に広島マツダに社名を変更し、2005年に松田哲也氏が6代目社長に就任しました。
2011年は海外事業を開始し、FCS(大連)技術開発有限公司に出資、株式会社FCS ワールド(現株式会社ブローダ)を設立し、モバイルアプリ事業に進出しました。
2016年には原爆ドームの横におりづるタワーをグランドオープン。
その後も広島を拠点とする企業7社をグループ傘下に収め、また企業6社を設立し、拡大を続けてきました。2023年にはホールディングス化し、ヒロマツホールディングスとなっています。
広島の豪雨災害やコロナ禍など経営環境の悪化がありながらも、2014年から7年連続200億円以上を記録している企業です。
これまで数多くの地域コングロマリット経営を行っている企業のうまくいっている形に「地域のその企業に対するイメージの転換」があります。
広島マツダさんであれば「地域の車屋さん」というイメージから「地域の有力企業」へ変わるような形です。
また、それができると採用力も高まりますね。
松田氏:
はい。事業の拡大では、まさにそのイメージの転換を狙いました。
行ったのは「これまでの広島マツダをすべてぶっ壊す」です。
それまでのわが社は、新卒社員しかおらず中途採用はゼロ、関連会社は数社ありましたが、全て広島マツダの自動車販売のための付随業務的なものでした。
広島マツダはマツダ創業の地の会社ですから、知名度はありますが、私は決して営業力があるとは思っていませんでした。
自動車ディーラーという仕事は将来的には厳しくなると考えていましたし、自動車ディーラーは就職人気ランキングでは下のほうに位置します。
休めずノルマは多い、でも給料は安い、そのようなイメージです。
将来は自動車ディーラー以外の道を考えていかなければならない。
そのためには多角化が必要だろうと考えました。
私は2005年に広島マツダの社長に就任した際「まずは本業で広島県一番になろう。
広島マツダとして勝てるようになろう」と宣言しました。
西日本で最大級のショールームを備えた宇品本店をオープンするなど、広島で一番になるための攻めの施策に力を入れました。
同時に多角化することも宣言しました。自動車販売はテリトリーがはっきりしているので、大阪や東京など国内のもっと大きなマーケットへの進出は難しい、ならば海外に行こう。
同時に広島で事業を広げるならば、自動車とまったく関係ないことを行っていこう。
そのすべてを行う。そう言ったのです。
鈴木:
それを25年前に始められたのですか。すごいですね。
松田氏:
それから始めたのが、中国人社員の新卒採用です。
今は当たり前ですが、当時は目新しかったですね。
中国で何をするかはまだ決まっていませんでしたが、まずは人を採ろうと決めて、彼らに事業の組み立てを任せてみることにしました。
中国人採用は地元でも話題になり、メディアからの取材も多々ありましたね。
まずは彼らが「新しいことをする存在」と社内に新鮮な空気を入れてくれました。
そして「中国人を採用した」という事実が、FCS 大連(現広松大連)というIT 企業が「一緒にやりませんか?」と声をかけてくることにつながります。
その会社の要望は「自分たちは開発はできても営業力がない。
広島マツダは営業の会社だから、営業をしてくれないか」でした。
それが縁で、中国企業とのつながりが強くなっていきます。
その後に別の中国人が入社して、新たな事業が立ち上がったりするようになりました。
まずは自動車販売など、本業の自動車に近いものから中国事業を進めていったのです。
担当コンサルタント

価値向上支援本部
アカウントパートナー推進部
マネージング・ディレクター
Keisuke Suzuki
鈴木 圭介
2007年株式会社船井総合研究所(現株式会社船井総研ホールディングス)に新卒で入社。法律事務所の事業戦略・マーケティング支援・組織開発に従事し、デジタルマーケティングを中心に変革を進め、業界を代表する事務所・士業グループを多数輩出。法律部門の責任者を経て、2021年より「中堅企業向けコンサルティングサービス部門」の立ち上げに参画し、特に20億~50億企業が100億企業になるためのコングロマリット企業化・ロードマップ策定に関する専門性を有する。「日本の未来を担う企業の成長を加速させる」ことをミッションに日々コンサルティングを行っている。2023年より同部門責任者(マネージングディレクター)に就任。『地域コングロマリット経営』(2023年)同文舘出版、『士業の業績革新マニュアル』(2015年)ダイヤモンド社等、多数の書籍を執筆。
お問い合わせ
CONTACT

